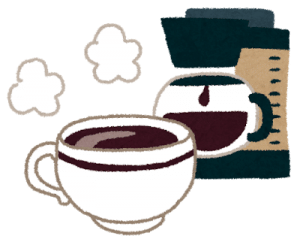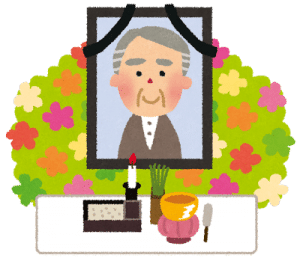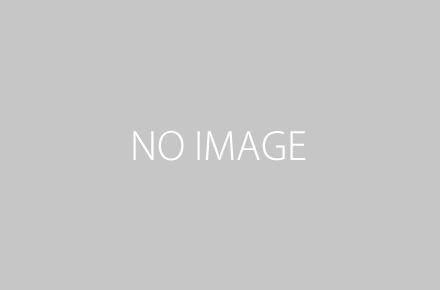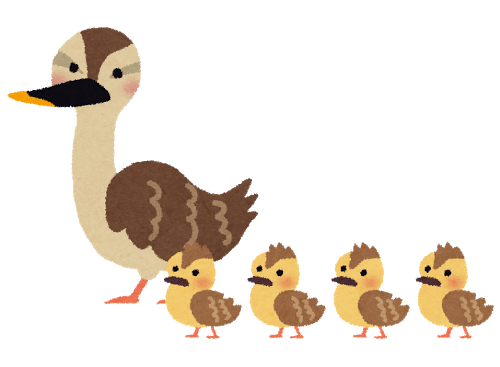知ってて損はない話(第1回)
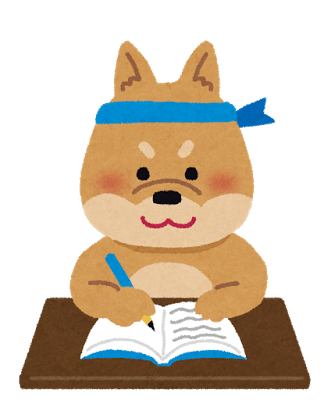
不動産取引と税金
不動産を手にいてる時や手放す時も,まずは税金を勉強することから始めましょう
なぜなら各種控除制度は,その制度を理解し,自ら活用(確定申告)しなければ,その恩恵を得ることはできません
税務署の職員が手取り足取り,節税の観点でアドバイスはしてくれませんよ
ポイント1 税制の非課税枠を活用しましょう
贈与税は高い
相続税より高い
贈与という行為に関する税金の知識については,一般的にはこの程度のイメージでしょうか
無償(タダ)でもらえる財産には,ガッチリ税金がかかる仕組みになっているわけです (+o+)
でも,贈与財産に対して非課税枠(年間110万円)があるのはご存知でしょうか
しかも,不動産が贈与財産の場合,市場取引価格ではなく固定資産税評価額をベースに計算されます
これ,すごく有利なんですよ (´ω`*)
例えば,市場取引価格が150万円の不動産があったとして,固定資産税評価額が100万円程度であれば贈与財産の非課税枠に収まりますので,贈与税は一切かかりません (*’▽’)
固定資産税評価額は,一般的には市場取引価格の7割程度で設定されるためです
不動産によっては6割程度で設定されている場合もあります
ここに現金・預金が150万円あったとして,生前に贈与したいと思っても150万円全額を渡すと40万円に贈与税が課税されることになります (+_+)
これが,150万円分の不動産を購入し,贈与(名義変更)すると,固定資産税評価額は1,500,000×0.7=1,050,000円前後になると思いますので,単年度あたりの贈与非課税枠の110万円内となり,税金がかからないわけです
これを活用すれば,固定資産税評価額110万円以内の価格相当額を共有持分として順次移転することで,非課税で不動産の名義を移転することだって可能になります
ただし,不動産そのものの資産価値が高い場合,年数はかかりますがね、、、 (;^ω^)
よく,資産形成するには不動産が有利といいますが,市場価格と課税価格の差額を税制が認められているところを利用している一面があります
ここで,ちょっとコーヒーブレイク
平成27年1月1日に相続税,贈与税の税制改正が行われています
改正前は遺産に係る基礎控除額(課税価格から無条件で控除できる額)は
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
でした
改正前は,妻と子どもが1人の家族で旦那さんが亡くなった場合,旦那さんの遺産が7,000万円以内であれば相続税は非課税になっていました
改正後は,基礎控除額が
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
と縮小されました
先ほどのケースで言うと旦那さんの遺産が4,200万円以上あれば相続税が発生することになりました
単純に6,000万円を現金で持っていて,相続が発生すれば1,800万円に課税されますが,これらを不動産に換価することで、、、、
6,000万円×0.7(不動産によっては0.5~0.6設定もあり)=4,200万円
と,一気に基礎控除額の範囲に持っていけるということになります
まあ,これだけの資産を保有している方は,なかなか見かけないかも知れませんが (;^ω^)
将来の相続税対策として,現金・預金を不動産に換価することが有効になる人は,今回の税制改正で確実に増えているということですね